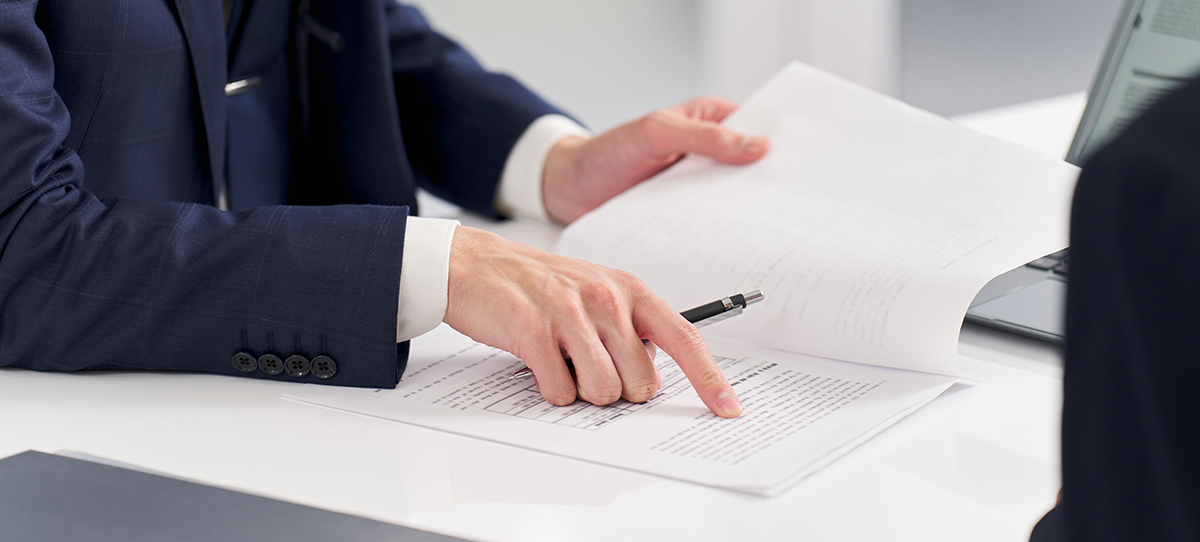そもそも相続の放棄はできるの?
相続が開始すると、被相続人の財産や債務(借金など)は、原則として相続人に引き継がれます。相続と聞くと、遺産としてのプラスの財産を受け取るイメージが強いかもしれませんが、実際にはマイナスの財産、つまり債務も一緒に相続されることになります。このとき、借金の方が多い場合等、相続によるトラブルを避けたい場合には、「相続放棄」という手段を選ぶことができます。
遺産分割協議で借金を相続しないとすれば相続放棄したことになる?
先日、お客様から、被相続人に借金がある相続のご相談で、お客様から、「『遺産は債務も含め全て長男が相続する。』という内容で遺産分割協議がまとまったら、次男は相続放棄したことなりますよね?」と質問を頂きました。
この質問について、結論から申し上げますと、これは、民法上の相続放棄ではありませんので、相続放棄とはなりません。
遺産分割の対象は、プラスの財産について行うものであり、借金(金銭債務)は遺産分割の対象にならないとされているからです(被相続人の金銭債務その他の可分債務は、法律上当然分割され、各共同相続人がその相続分に応じてこれを承継するものと解すべきであるとした最高裁判所昭和34年6月19日判決参照)。
したがって、遺産分割協議書に上記のとおり定めがあったとしても、債権者がその定めを承諾しない限り、上記の定めは相続人間で金銭債務をどのように負担するのかということの合意をしたという意味しかなく、次男は債権者に対して、「私は相続放棄しました。なので、借金は、長男に請求してください。」とは言えません。
このようにご説明し、下記の相続放棄を含め、改めて相続人間でどうするかを再検討して頂くように促しました。
相続放棄するためには家庭裁判所へ手続きが必要
借金の返済義務から完全に逃れるためには、家庭裁判所での相続放棄の手続きが必要です。
相続放棄は、家庭裁判所に戸籍等の書類と一緒に「相続放棄申述書」という書類を提出して行う手続きです(民法第938条参照)。この手続きが受理されれば、相続の放棄をした方は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法第939条)。これにより、相続放棄をした方は借金から解放されます。
相続放棄の注意点
相続放棄が受理されますと当然ですが、プラスの財産も受け取れなくなります。
また、相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと法律で定められています(民法第915条第1項)。この期間を過ぎてしまうと、原則として相続放棄はできなくなってしまいます。
最後に、相続放棄が受理されると、相続放棄をした方は初めから相続人でなかったものと扱われますので、次の順位の相続人に相続する権利が移ります。例えば、親の相続(父は先に死亡しており、今回は母が被相続人の場合)について子が相続放棄をすると、親の親(子の祖父母)、親の親が死亡していた場合は、親の兄弟姉妹(子の叔父・叔母)が相続人になる可能性があります。
借金がある場合、その借金の返済義務が次の相続人に引き継がれることになりますので、安易な気持ちで相続放棄をすると、思わぬ形で親族に迷惑をかけてしまう可能性もあり、相続人全員で状況を把握し、慎重な検討が必要です。
相続放棄のご相談は当事務所まで ~初回相談は無料~
正しい理解と準備が安心できる相続につながります。「借金を相続したくない!」という明確な意思がある場合は、まずは当事務所にご相談ください。正しい知識を身につけ、ご自身の将来と大切なご家族を守りましょう。当事務所は、相続のご相談はもちろん、相続放棄のサポートもさせて頂いております。初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
著者:代表司法書士 佐々木 翔
東京都世田谷区南烏山4丁目3番8号マノアール世田谷301
司法書士あおぞら法務事務所